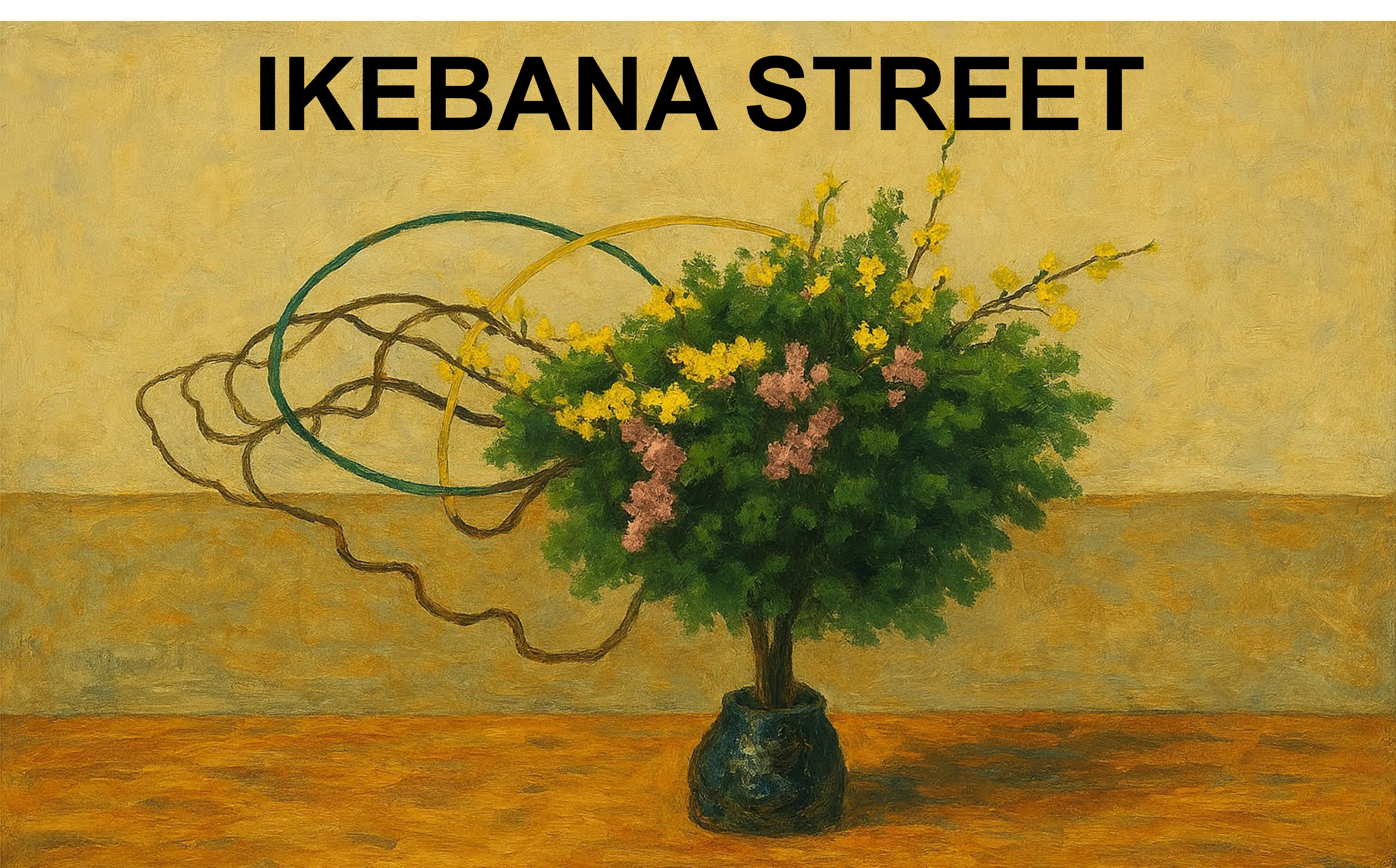いけばなは、仏教の供花や日本古来の自然観を背景に、室町時代に芸術としての形を整えていきました。この時代、政治的には不安定でしたが、文化面では禅宗を中心とした簡素で精神性の高い美意識が広まりました。
書院造と床の間の誕生
室町時代には、武家の邸宅に「書院造(しょいんづくり)」と呼ばれる建築様式が取り入れられ、室内の床の間(とこのま)に花や掛け軸を飾る習慣が生まれました。これにより、花を飾る文化が室内装飾の一部として定着していきました。

立花の成立と池坊専慶
この時期、京都・六角堂の僧侶である池坊専慶(いけのぼう せんけい)が、仏前に花を供えるだけでなく、構成美や象徴性を備えた花の形式を打ち立てました。これが「立花(りっか)」と呼ばれる様式で、一本の主枝を高く立て、天・地・人の秩序を表すように構成されます。松や柳、草花などを用い、自然界の風景や宇宙の秩序を一つの花の中に表現しました。

芸術としての体系化
立花は、武士階級の精神修養や教養の一つとして受け入れられ、花の生け方に関する理論や思想をまとめた「花伝書(かでんしょ)」も登場しました。これにより、いけばなが型と理論を備えた芸術へと進化していきました。
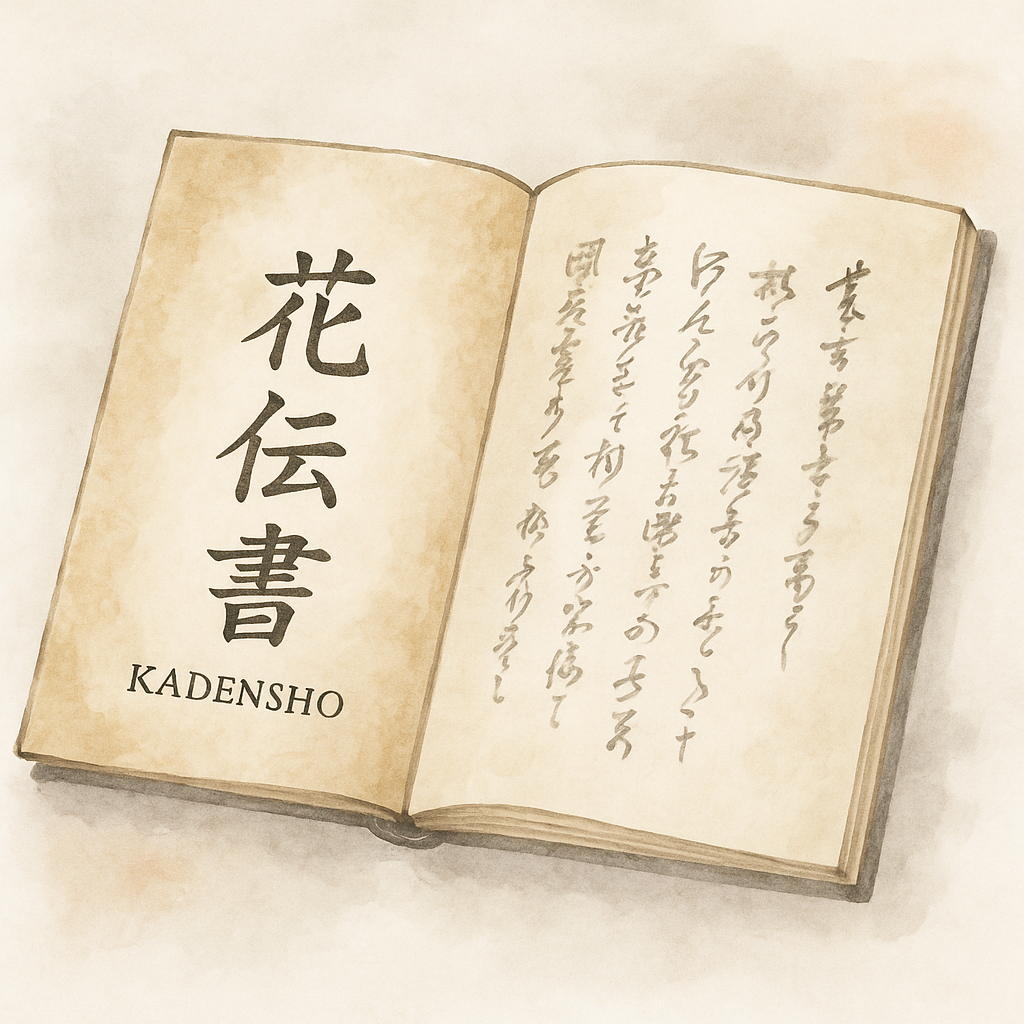
海外文化との関係
室町時代、日本は明(中国)との勘合貿易を通じて文化的交流を持っていました。禅宗の影響も中国から強く受けており、その中で「静」「空」「無」のような精神性を重視する芸術観が日本の文化にも根づいていきました。ただし、いけばなそのものが海外文化から直接的に取り入れた技法で構成されたわけではなく、日本国内で育った花に対する感性が中心となって発展したことは変わりありません。
庶民との関わり
室町時代のいけばなは、主に寺院や武士階級、あるいは公家など限られた層の中で行われていました。庶民が自由にいけばなを楽しむようになるのは江戸時代以降のことですが、室町末期には茶の湯の広がりとともに、花を飾る文化が徐々に町人階級にも浸透しはじめたとする説もあります。
まとめ
室町時代はいけばなが「信仰の行為」から「構成を持つ芸術表現」へと移行していく重要な時期でした。池坊専慶の立花様式や花伝書の登場は、今日の華道の基礎を築いた出来事といえるでしょう。次回は、江戸時代に入り、いけばなが流派として分化し、庶民文化へと広がっていく様子を見ていきます。